スポンサーサイト
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
大阪市職員へのアンケートがやばい
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
大阪市職員へのアンケートがやばいというので見てみた。
これは、捏造などでなければ違法じゃないのかしら。
【前提となる事実】
・地方公務員は、中立性確保のため、政治的自由や労働権が一部制約される(地方公務員法37条などを参照)
・もっとも、労働組合結成そのものは適法(×争議権 ○団結権)
・大阪市労組が政治的中立性(同法36条)に反し、前市長の支援を求める活動をしていたのではないかという疑惑が発生(いわゆる「労組職員リスト問題」)
・大阪市が調査に乗り出し、本件アンケートを実施
・趣旨としては、上記疑惑につき外部窓口に対する内部通報を義務付けるもの(特定候補への投票を呼びかけられたことはあるか、勧誘者はだれか、など)
・しかし、質問項目には政治活動参加への有無・内容、労組が影響力を持つと思うかなど思想に関係するものや不当労働行為にみえるものも含まれていた
・記名式(氏名・職分などを明かす)+市長の業務命令+不正確な回答には処分もあり(アンケートというよりは、報告命令書か?)
・提出は、庁内ポータルまたは所属部局を通じて行う
・ところで…自治体職員の思想を調査した先例あり
・川崎市が職制機構を通じて主査以上の市職員全員に対し、政党機関紙の購読に関して質問
・こちらの経緯は、共産党市議会議員が市職員に赤旗の購読を勧誘したとして、問題になったというもの
・勧誘に「圧力を感じたか」という質問項目が含まれる
・国家賠償訴訟へ
・第一審・控訴審とも公務員側敗訴(現在も係属中?)
・しかし、東京高裁は傍論ながら「本件アンケート調査の質問項目の中には思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあるといわざるを得ないものがあり、回収方法についても本件においては結果的に問題がなかったものの、不十分であると言わざるを得ない点が認められるほか、本件アンケート調査が実施された理由・目的と、実施に伴う問題点や実施に伴う様々な負担、得られた成果などとを比較すると、本件アンケート調査の実施がその実施方法も含めて最善の措置であったとはいい難く、実施すること自体の当否や実施するとしてもより穏当な方法について、検討が尽くされたとはいえず、適切な判断がされたとは認め難いところもある」としている
【検討】
・両事例とも公務員の政治的中立性への疑義を契機とする
・ただ、川崎市が市議会議員への疑惑であるのに対し、本件は労組そのものに対する疑惑(労組加入していない職員にとっては同じ第三者ともいえるが)
・限界事例っぽい川崎市の場合は無記名式だったらしいが、本件は記名式(この差は大きいだろうが、どの程度判断に影響するか)
・「勧誘に圧力を感じたか」と「労組はどの程度影響力を持つと思うか」は、同じといえるか(ともに内心を尋ねるものだが、前者は具体的事例についてであり、後者は一般論とも思える。でも、一般論だとすると、違法行為調査という目的との関係で、関連性が薄くなるだろう)
・政治活動の有無・内容への質問は、疑惑への関与を聞くものにとどまるか(リスト問題をこえて聞いているようにもみえる)
【考えられる争点】
・労組の違法行為を調べるにあたり、適切な質問項目か
・不適切な質問項目があるとすれば、それは不利益性があるか
・不当労働行為にあたるか、また、思想良心の自由やプライバシー権の侵害にあたるか
・回収方法は十分か(所属部局を通じて外部窓口提出しているが、労組加入等の情報を見られるおそれはないか)
・アンケート実施により得られる成果はどのようなものか
・「より穏当な方法」としてどんなものが考えられるか
・高裁は、実施に伴う負担と得られた成果を比較考量しているが、この手法は妥当か
※ なお、地方公務員法58条は労組法の適用を除外している。ただ、これは地方公共団体たるもの、労組法7条の不当労働行為はしないだろうということを前提に立法しているらしい。そうすると、地公法56条を介して、労組法7条に関する逸脱は、国賠上の違法になるっぽい(ややこしやー)
※ 上記の労働法上の違法とは別に、憲法上の問題も生じている
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
<< バイク移動してる姉が飼ってる犬 | ホーム | バーナンキの説明でばっさりと >>
コメントの投稿
ライフハック
ゆっくり用作業用ツール一覧
- WEB計
- 黄金比算出ツール
- Manage Twitter
- Twitterのフォロワー管理ツール
- 勝つーる dat
- 2ちゃんねるスレまとめ支援ツール。いつもお世話になっております。
- カテゴリー別配色アイディア100
- webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
- ポンデリンク
- amazon画像リンク作成ツール。便利!!
- WebWait
- Webサイトが完全に開き終わるまでの時間を計測してくれる。
- CLEAN CSS
- CSSファイルをお掃除してくれる。
- Loads.in
- WEBページを読み込んだ際、どこを読み込むのに時間がかかっているかをを視覚的に表してくれる。
- ScriptSrc
- jQueryをHTMLに書かなくても、GoogleでホスティングしたjQueryを読み込んでくれる神ツール。
- 魔理沙 on Twitter Counter.com
- フォローされた人数の推移がわかる。
- CSS Lint
- CSSのコーディングをチェックしてくれる神Tool
- 少しのコードで実装可能な20のjQuery小技集
- Webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
ゆっくりプロフ
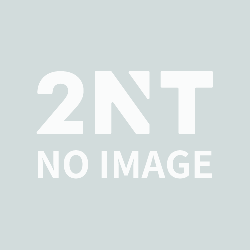
Author:たくあんまりさ
たくあんまりさをフォロー
【ブログ管理者様へ】
当ブログについて
相互RSS依頼、随時募集中です。逆アクセスを参考に9割ほど登録させて頂きます。詳しくは当ブログについて:aboutを閲覧して頂ければ幸いです。
それではゆっくりしていってね!!
【読者様へ】
「ゆっくりしていってね!!」では毎日「海外画像」「海外記事翻訳」を配信しております。その記事以外は全て他ブログ様の記事を紹介しております。手動のアンテナです。
面白かった、スレタイで吹いたもの...etc、配信ネタは厳選しております。
「時間がなくてまとめブログのチェックなんてしてらんない!」
と嘆くそこのアナタ、「ゆっくりしていってね!!」は時間に追われる現代社会人のアナタのためのようなブログです。
それではゆっくりしていってね!!
ネットで人気爆発中!!
月別アーカイブ
相互サイトゆっくリンク
- 中国的爆発日記
- コピペ いんざわーるど(・∀・)
- 東亜+News速@2ch
- 8day-beauty pictures
- xanadu
- 萌え豆にゅー
- なんか憑かれた速報
- 世界ランク速報
- ちゃんねるはそのままで!
- ハム・ソーセージ速報
- お宝エログ幕府
- ラビット速報
- (´・ω・`)ショボーン速報
- 笑韓
- とすぺるッ!!
- お絵かき速報
- seiyu fan
- Chyborg
- ラジック
- スーパーヒーロー速報2ch
- 【SS宝庫】みんなの暇つぶし(ノ^^)八(^^ )ノ
- 2ちゃんを斬る!
- ぱんだ とらんすれーたー
- オタク.com
- ゲハ速
- ふよふよ速報。
- 芸能人の裏の顔
- 半角ピンクエログ
- ダラ見堂
- ゆっくりしていってね!!!
- 2ちゃん市況2板応援ブログ
- FUNNY-IMAGE
- 管理画面


