スポンサーサイト
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
本に載っているのは「最新」の情報ではない。書いたものが本になるまでには、かなりの時間がかかるのだ
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
先日も書いたが、本に載っているのは「最新」の情報ではない。書いたものが本になるまでには、かなりの時間がかかるのだ。
さて、研究は 「早い者勝ち」の世界だから、誰も手をつけてないことか、まだあまり手がつけられていないことをやることになる。そのため取り扱うトピックはよりマイナー になっていく。
どマイナーなトピックなど、書いても売れないから、書店で買える書籍にはならない。では、それはどこにあるか?
答:博士論文にある。
新しく、いっぱしの研 究者になろうとする者が書く博士論文。
新参者が、すでに分厚い先行研究がある(その業界では)メジャーなトピックにチャレンジしようと いうのは、これまでの蓄積をひっくり返せる何年に一度出るか出ないかという実力者か、単なる勘違い野郎である。
もっと慎ましやかな庶民研究者 は、もっと隅っこで、ほじくるような研究をやる。あるいはまだ、あまり手がついていない目新しいことをやる。
イントロダクションには、 「@@についてはこれまでたくさん論じられているのに対して、**について書かれたものは、$$と##ぐらいのもので、***ともなるとほとんど研究が無 い(だから、おれがやる)」といったことが宣言されるだろう。
博士論文は、若手研究者のニッチ狙いの残骸だ。しかし立場を変え れば、マイナー・トピックの宝庫だ。
しかも、博士論文は、それを書いた者が、いっぱしの研究者と名乗ってよい程度の、研究のイ ロハは身につけていることを、証拠立てる「物証」である。
書いた者が、先行研究を徹底的に調べ上げ、それらと自分の研究との位置関係を明示し、 研究者コミュニティのなかに自身を位置付けるものでなければならない。
これも、立場を変えてみれば、中身はつまらなくても、自分の研究の前提/コンテクストとなる先行研究については、ほぼこれ以上ないくらい調べ上げ、これ までの研究の流れと蓄積が適切に要約されているはずである。でなきゃ、突き返されてるだろう。
というわけで、博士論文 は、どマイナーな、あるいは最新すぎて解説書なんてないトピックについて、手っ取り早く概要を知り、加えて網羅的な(抜けの少ない)文献リストを入手する のに利用できるのだ。
同様の理由から、メジャーなトピックでも、最近の博士論文であれば、研究概要としても、文献リストとしても、他よりも新鮮 なものが入手できる可能性が大である。
via:博論は宝の山/テーマが決まったら真っ先に博士論文を読もう 読書猿Classic: between / beyond readers
http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-274.html
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
<< ソーシャルマーケティングがハンパない会社を辞めて、スタートアップを起ち上げる僕の目指す世界 | ホーム | 年金の支給開始が70歳になったら、「金融商品」としての損得はどうなるのだろうか? >>
コメントの投稿
ライフハック
ゆっくり用作業用ツール一覧
- WEB計
- 黄金比算出ツール
- Manage Twitter
- Twitterのフォロワー管理ツール
- 勝つーる dat
- 2ちゃんねるスレまとめ支援ツール。いつもお世話になっております。
- カテゴリー別配色アイディア100
- webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
- ポンデリンク
- amazon画像リンク作成ツール。便利!!
- WebWait
- Webサイトが完全に開き終わるまでの時間を計測してくれる。
- CLEAN CSS
- CSSファイルをお掃除してくれる。
- Loads.in
- WEBページを読み込んだ際、どこを読み込むのに時間がかかっているかをを視覚的に表してくれる。
- ScriptSrc
- jQueryをHTMLに書かなくても、GoogleでホスティングしたjQueryを読み込んでくれる神ツール。
- 魔理沙 on Twitter Counter.com
- フォローされた人数の推移がわかる。
- CSS Lint
- CSSのコーディングをチェックしてくれる神Tool
- 少しのコードで実装可能な20のjQuery小技集
- Webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
ゆっくりプロフ
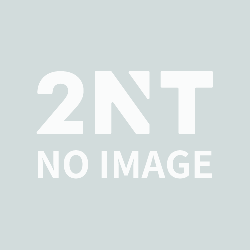
Author:たくあんまりさ
たくあんまりさをフォロー
【ブログ管理者様へ】
当ブログについて
相互RSS依頼、随時募集中です。逆アクセスを参考に9割ほど登録させて頂きます。詳しくは当ブログについて:aboutを閲覧して頂ければ幸いです。
それではゆっくりしていってね!!
【読者様へ】
「ゆっくりしていってね!!」では毎日「海外画像」「海外記事翻訳」を配信しております。その記事以外は全て他ブログ様の記事を紹介しております。手動のアンテナです。
面白かった、スレタイで吹いたもの...etc、配信ネタは厳選しております。
「時間がなくてまとめブログのチェックなんてしてらんない!」
と嘆くそこのアナタ、「ゆっくりしていってね!!」は時間に追われる現代社会人のアナタのためのようなブログです。
それではゆっくりしていってね!!
ネットで人気爆発中!!
月別アーカイブ
相互サイトゆっくリンク
- 中国的爆発日記
- コピペ いんざわーるど(・∀・)
- 東亜+News速@2ch
- 8day-beauty pictures
- xanadu
- 萌え豆にゅー
- なんか憑かれた速報
- 世界ランク速報
- ちゃんねるはそのままで!
- ハム・ソーセージ速報
- お宝エログ幕府
- ラビット速報
- (´・ω・`)ショボーン速報
- 笑韓
- とすぺるッ!!
- お絵かき速報
- seiyu fan
- Chyborg
- ラジック
- スーパーヒーロー速報2ch
- 【SS宝庫】みんなの暇つぶし(ノ^^)八(^^ )ノ
- 2ちゃんを斬る!
- ぱんだ とらんすれーたー
- オタク.com
- ゲハ速
- ふよふよ速報。
- 芸能人の裏の顔
- 半角ピンクエログ
- ダラ見堂
- ゆっくりしていってね!!!
- 2ちゃん市況2板応援ブログ
- FUNNY-IMAGE
- 管理画面


