スポンサーサイト
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
ところで、パソコンのスクリーンを眺めていても発見できない誤字脱字が、プリントアウトすると容易に見つかるという経験は、誰もが一度はあるのではないだろうか
最強の無料動画サイトが帰ってきたwwww
Kindleが採用しているのはE Inkという電子ペーパーシステムである。凸版印刷のE Ink 電子ペーパーページの説明がわかりやすいと思われるが、最大の特徴は透過光ではなく反射光であるということだ。
紙の本もそうだが、物体に反射した光が目に入る。これが反射光。一方、テレビやパソコンのモニターはブラウン管や液晶やプラズマディスプレイが光を発している。これが透過光メディアだ。E Inkを使ったキンドルは、電子本デバイスでありながら、透過光ではなく反射光なのである。
反射光と透過光の違いは、実は非常に重大な意味を持っている。その意義について、丸田一『「場所」論―ウェブのリアリズム、地域のロマンチシズム (叢書コムニス08)』が非常にわかりやすくまとめているので、少し長くなるが引用したい(178~179ページ)。ここでは、映画も反射光メディアに含まれている。
まず、確認したいのが、「透過光」がもたらす「距離埋没効果」である。パソコンのモニター、携帯電話をはじめ、ウェブ空間のインターフェースは、ほとんどが透過光によるスクリーンである。スクリーンにはブラウン管や液晶、有機ELなど様々な映像表示方式が採用されているものの、どれも発光源を持ち、スクリーン表層を透過する光線で画面を表示することに変わりない。透過光による表示は、反射光の表示に比べて現前性が高く、利用者の身体とスクリーンとの間に横たわる十数センチ~数十七ンチという距離を埋めてくれる。
透過光が強い現前性をもたらすことは、マクルーハンも『メディアの法則』で指摘している。マクルーハンは、映画の観客を二分して、一方には普通の映画と同じように反射光によって、もう一方には透過光によって同じ映画を鑑賞させるというハーバート・クルーグマンの実験を取り上げている。反射光のグループの感想は、映画を物語や技術に注目して理性的に分析し、批判する傾向が優位を占めたのに対して、透過光のグループでは、好き嫌いという情緒的で、主観的な反応が優位を占めた。
反射光の映画において観客は、スクリーンと身体との物理的な距離を保ったまま、対象としてスクリーン上を見ている。この距離が映像を対象化し、観客に分析的で批判的な見方を与える。一方、透過光のテレビでは、スクリーンを越えて到達する光に視聴者が深く差し込まれてしまうので、映像は実際のスクリーン面から離れて、観客の目や身体を擬似的なスクリーンにして現前する。このように透過光の場合、観客は対象とうまく距離をとれず、場合によっては対象と位置的に重なってしまうことが、観客に情緒的、主観的な見方を与えるといえるだろう。
ところで、パソコンのスクリーンを眺めていても発見できない誤字脱字が、プリントアウトすると容易に見つかるという経験は、誰もが一度はあるのではないだろうか。これも「反射光と透過光」である程度説明ができる。スクリーンの透過光で文字を読んでいても見逃しがちな誤字脱字は、プリントアウトした紙の反射光で読むと、対象を分析的、批判的に捉えることができるので、より発見されやすいといえる。
このように現前性の強い透過光が、ウェブ空間のインターフェースに用いられているのは偶然ではないだろう。現前性の高い透過光は、スクリーンと利用者の身体との。間にある物理的な距離を埋没させ、スクリーンを没対象化させてしまう。これがスクリーンというインターフェースを準没入型に変えるのである。
Amazon Kindle(アマゾン・キンドル):「反射光の電子ブック」という革命的に新しいメディア - 絵文録ことのは - BLOGOS(ブロゴス) - livedoor ニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/4526848/
Twitter上で人気の記事まとめ
Amazon全国売り上げランキング
殿堂入り記事一覧
ふえぇ…ここまで読んでくれてありがとうだよぉ…
ところで、パソコンのスクリーンを眺めていても発見できない誤字脱字が、プリントアウトすると容易に見つかるという経験は、誰もが一度はあるのではないだろうか |
[ 2012/01/06 16:30 ]
ネタ全般 |
TB(-) |
CM(0)
<< 全自動掃除機のルンバ530。ネットで半額以下に。 | ホーム | 【スマフォ】x【Bluetooth】x【スピーカー】コスパ最強のブームボックス TS800。 >>
コメントの投稿
ライフハック
ゆっくり用作業用ツール一覧
- WEB計
- 黄金比算出ツール
- Manage Twitter
- Twitterのフォロワー管理ツール
- 勝つーる dat
- 2ちゃんねるスレまとめ支援ツール。いつもお世話になっております。
- カテゴリー別配色アイディア100
- webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
- ポンデリンク
- amazon画像リンク作成ツール。便利!!
- WebWait
- Webサイトが完全に開き終わるまでの時間を計測してくれる。
- CLEAN CSS
- CSSファイルをお掃除してくれる。
- Loads.in
- WEBページを読み込んだ際、どこを読み込むのに時間がかかっているかをを視覚的に表してくれる。
- ScriptSrc
- jQueryをHTMLに書かなくても、GoogleでホスティングしたjQueryを読み込んでくれる神ツール。
- 魔理沙 on Twitter Counter.com
- フォローされた人数の推移がわかる。
- CSS Lint
- CSSのコーディングをチェックしてくれる神Tool
- 少しのコードで実装可能な20のjQuery小技集
- Webクリエイターボックス(^ω^)ペロペロ
ゆっくりプロフ
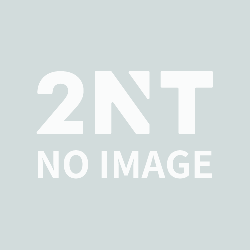
Author:たくあんまりさ
たくあんまりさをフォロー
【ブログ管理者様へ】
当ブログについて
相互RSS依頼、随時募集中です。逆アクセスを参考に9割ほど登録させて頂きます。詳しくは当ブログについて:aboutを閲覧して頂ければ幸いです。
それではゆっくりしていってね!!
【読者様へ】
「ゆっくりしていってね!!」では毎日「海外画像」「海外記事翻訳」を配信しております。その記事以外は全て他ブログ様の記事を紹介しております。手動のアンテナです。
面白かった、スレタイで吹いたもの...etc、配信ネタは厳選しております。
「時間がなくてまとめブログのチェックなんてしてらんない!」
と嘆くそこのアナタ、「ゆっくりしていってね!!」は時間に追われる現代社会人のアナタのためのようなブログです。
それではゆっくりしていってね!!
ネットで人気爆発中!!
月別アーカイブ
相互サイトゆっくリンク
- 中国的爆発日記
- コピペ いんざわーるど(・∀・)
- 東亜+News速@2ch
- 8day-beauty pictures
- xanadu
- 萌え豆にゅー
- なんか憑かれた速報
- 世界ランク速報
- ちゃんねるはそのままで!
- ハム・ソーセージ速報
- お宝エログ幕府
- ラビット速報
- (´・ω・`)ショボーン速報
- 笑韓
- とすぺるッ!!
- お絵かき速報
- seiyu fan
- Chyborg
- ラジック
- スーパーヒーロー速報2ch
- 【SS宝庫】みんなの暇つぶし(ノ^^)八(^^ )ノ
- 2ちゃんを斬る!
- ぱんだ とらんすれーたー
- オタク.com
- ゲハ速
- ふよふよ速報。
- 芸能人の裏の顔
- 半角ピンクエログ
- ダラ見堂
- ゆっくりしていってね!!!
- 2ちゃん市況2板応援ブログ
- FUNNY-IMAGE
- 管理画面


